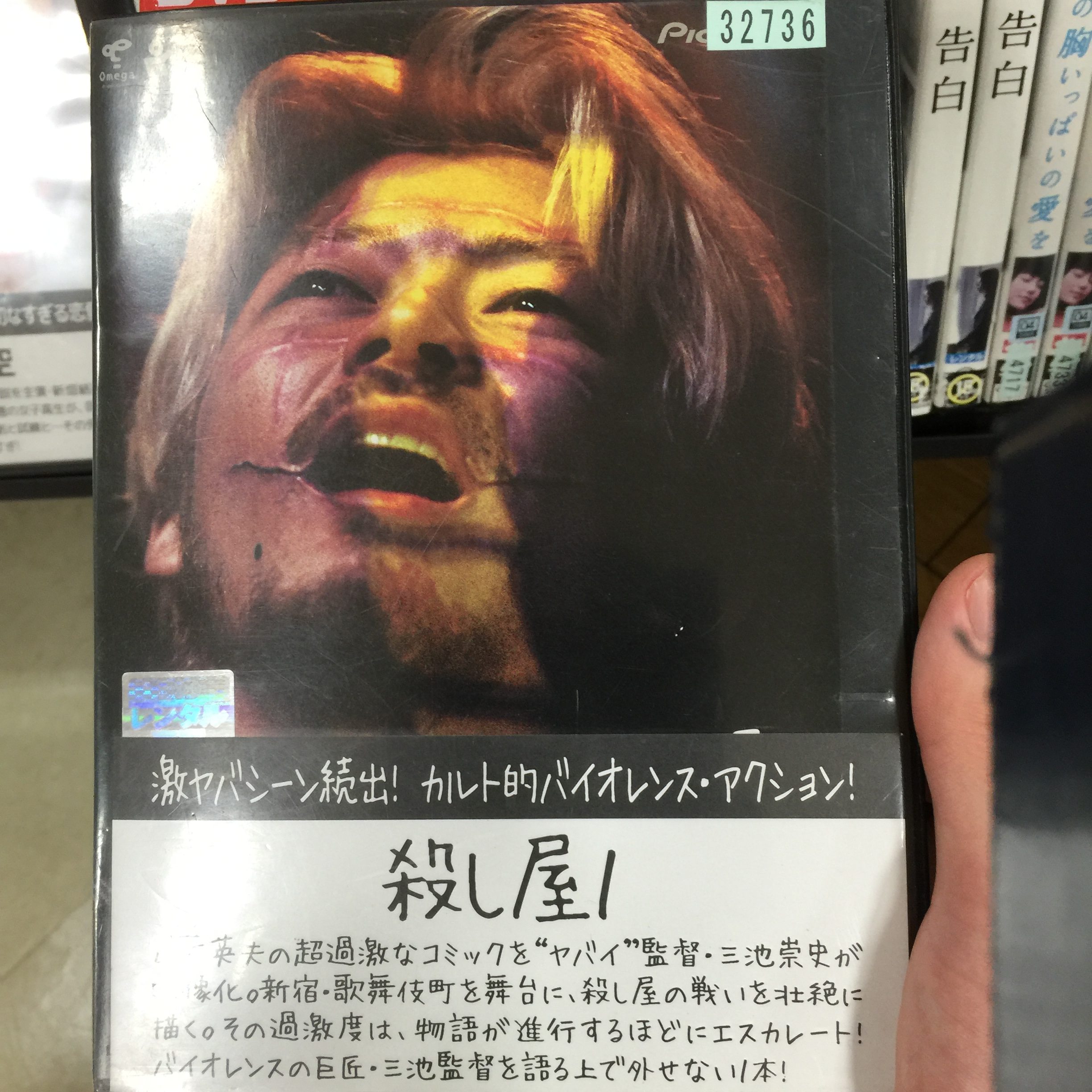「デンデラ」を見た感想
「デンデラ」という映画をさっき見た。あらすじとしては、老年を迎え、姨捨山に捨てられた主人公が、死を覚悟し、雪山に寝そべっていると、元気な二人の老婆が現れる。彼女たちに連れられた先には同じように捨てられた老婆たちが「町」(デンデラ)を作っていた。デンデラの長は自分たちを捨てた町に対して敵意を燃やし、いつか総勢五十人の武装化した老婆たちを連れて、村人たちを虐殺しようと企んでいる。しかしその後、デンデラが熊に襲われたり、襲撃当日に雪崩にあったりして、戦力が減反し、物語の主軸はいかに熊を撃退するかに変わっていく。村人の大半を熊に食われて落ち込む主人公は一人武器を片手に熊を殺しに山へ出かける…
なんか自分たちを虐げた村人たちに復讐する話が、いつの間にか雪崩とか熊とかの「自然災害」をいかに克服するかに話が変わっていて、不満だった。同じ人間である村人を殺す葛藤や、復讐することの意味等の話を見たかった。
でも映画の中で雪崩や熊も意志を持った人間のように捉えられていて、それらに対抗する意志を持つことが大事みたいなメッセージだったけど、現代科学に毒されている僕は「そりゃ雪崩起きて逃げなかったら死ぬだろ」とか「熊に棒で立ち向かっても死ぬだろ」とか思って冷めてしまった。なんだろうな、たとえ無謀だと分かっていても、立ち向かう老婆たち、かっけーと映画的には思ってほしいんだろうけど、目の前で素手で立ち向かって死んでいる老婆たちをたくさん見ているわけだから、それでも素手で立ち向かう老婆はただのアホとしか映らなかった。
それに途中で主人公はデンデラを出て熊などに襲われない「良い土地」を見つける旅に出るという話をするんだけど、熊に復讐することに集中しすぎて、一番将来性のある、その計画がまったく着手されなかったのも残念だった。
映画を見ていて、唯一発見らしきものがあったとすれば、女子校のノリってあんな感じなんだろうなということ。人前で平気で屁をこいたり、小熊倒してその肉を食べるときに「ババアのくせに性のつくもの食べてどうするんだ!」という会話をしたり。デンデラは男性排除の女性社会だったので、そのへんが参考になったと言えば、なった気がする。
以上、デンデラを見た感想でした!